農と食の周辺情報
一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介
一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介

1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー
 白井 洋一
白井 洋一除草剤グリホサートは殺虫剤ネオニコチノイドとともに、社会面で話題になる農薬だ。欧州連合(EU)ではグリホサートの再更新・承認をめぐって、加盟国がまとまらず、混乱する状況が続いていた。今年(2023年)も、12月15日の有効期限切れが迫る中、迷走していたが、11月16日、EUの行政府である欧州委員会は、委員会の専決として10年間の更新を決めた(欧州委員会、2023年11月16日)。
2016年以来繰り返された再更新をめぐるドタバタ劇と比べて、欧州委員会の強行姿勢はやや意外だった。EUのグリホサート騒動を振り返るとともに、米国の発がん性と環境リスクをめぐる話題も紹介する。
参考:「グリホサート 最近の欧米事情 サイエンスを離れた悲喜劇続く」(2022年7月27日)
EUでは農薬の使用認可は原則15年ごとに更新される。グリホサートは2016年6月に再更新される予定だったが、2015年3月、世界保健機関 (WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)が「グリホサートはおそらく発がん性がある」とグループ2Aにランクしたことで、状況は一変した。
発がん性リスクを理由に環境系や左派系の政治家集団は承認反対、中立系でも棄権や様子見の投票が増え、有効投票数に達しなかった。EU27か国による有効票とは、15国以上かつ人口比で65%以上必要だ。15国以上が賛成しても、人口の多いフランス、ドイツなどが反対(または棄権)すると有効票には達しない。
2016年6月はとりあえず1年半延長した。2017年も最初の投票では決まらなかったが、最終的に大国ドイツが棄権から賛成に回り5年間延長で決着した。ドイツのメルケル首相(当時)は「農業担当大臣が独断で賛成票を投じた」と不満を表明したが、農業大臣の更迭もなく、ドイツを含めEU各国はその後もグリホサートを使い続けてきた。
5年後の2022年12月も、常設委員会、農業閣僚会議ともに有効票数に達しなかったが、欧州委員会の専決で1年間だけ延長した。1年としたのは翌年までに欧州食品安全機関(EFSA)の安全性審査結果がでるからという理由だった。
2023年7月、EFSAはグリホサートの更新は妥当とし、発がん性のリスクも現時点では確認されないと発表した。EFSAのほか欧州化学品庁(ECHA)も同様の結論であり、その他の国でも発がん性を含め重大な健康リスクを指摘した審査機関はない。IARCの発がんランクだけが異端だ。
2023年も常設委員会(10月)、審査委員会(11月)とも有効投票に達しなかったが、11月16日の審査委員会での不成立の後、即日欧州委員会は専決で10年間の延長を決定した。5年間に値切って妥協するのではなく、10年延長という初心を貫いた強硬姿勢はやや意外だった。
今回、フランス、ドイツ、イタリアなど人口大国はそろって棄権したが、EUのルールでは欧州委員会決定に従わなければならない。これから10年間、2033年までこのままでいくのだろうか?
国または地域レベルで使用禁止にするには、環境や生物多様性に重大なリスクがあると科学的に認められた場合だけである。発がん性など健康リスクでも根拠のある新知見が出てきたら、再検討することになる。ただし怪しげな科学論文が出たぐらいではだめだ。
フランスとドイツは国内でのグリホサート使用を数年以内で禁止する予定だが、代わりの有効な除草手段は開発されていない。フランスはグリホサートを使わず農作業する場合に特例予算を出す案を出したが、作業の手間が増えるだけで農家の評判はよくない(EurActiv、 2023/01/13)。
今回の投票で面白いのは、国内でグリホサートの使用を禁止するはずのフランス、ドイツが反対ではなく、棄権に回り、最終判断を欧州委員会に任せたことだ。なぜ国内政策と一致する反対票を投じなかったのだろうか。除草剤を使わないでも雑草防除はできるが、その分時間と労力は大変なものだ。有機農業者は別として、多くの農業者はそれを実感している。農薬嫌いの政治家が政権を担っているフランスやドイツの今後の動きが気になるところだ。
米国でもグリホサートの再更新・承認で揺れている。2022年9月、米国環境保護庁(EPA)はグリホサートの再更新手続きを一旦中止し、2026年までに再審査すると発表した(EPA,2022/09/23)。
これは環境リスクの評価について環境活動団体が起こした訴訟によるものだ。ここまでの経緯を「米国環境保護庁 グリホサート暫定評価書取り下げ これまでとこれから」で見てみる(Farm Press,2022/10/04)。
米国でも農薬は15年ごとに再評価される。EPAは2009年に再更新の審査を開始。その後、複数回の審査、意見募集(パブリックコメント)をおこない、2020年1月に暫定的な使用を認める決定をした。3月、自然資源保護協会など環境団体が、EPAは環境リスクに関して十分に調査をしておらず、決定は種の保存法(Endangered Species Act)に違反すると訴えた。
2022年6月、控訴裁判所は原告の主張を概ね認め、EPAに対して、10月1日までに追加調査の結果を提出するよう命じた。
2022年9月21日、EPAは10月1日までに裁判所の要求するデータは準備できないので、暫定的使用決定を撤回し、2026年までに改めて再評価書を提出すると発表した。
これでグリホサートが使用できなくなるかというとそうではない。EPAは使用禁止と判断したのではなく、使用決定を一時的に撤回したので、市場での流通、現場での使用は今まで通りというのが、米国の連邦レベルでの解釈だ。環境団体は州レベルでの禁止など、様々な攻撃を仕掛けているが、2023年12月現在、グリホサートは販売され、使用され続けている。
グリホサートに限らず、EPAの農薬審査は不十分という理由で、環境団体から訴えられ、安全性の有無よりも、審査の量と質の手続き面で、裁判で負けることがある。EPAは裁判による敗訴を回避するため、2022年4月に事前の環境リスク評価を重視し、種の保存法に則ったリスク地域の設置など、「絶滅危惧種を保護し、持続可能な農業を支えるための計画」を提案した(2023年12月時点で、まだ決定していない)。
米国では発がん性をめぐってもメディアに登場する。加州はグリホサートに厳しく、製品に「発がん性のリスクがある」と表示を義務づけている。2023年11月7日、控訴裁判所は発がんリスクには科学的に十分な根拠がなく、連邦レベル(米国憲法に相当)では違憲として、加州の表示義務を否定した(UsAgNet、2023/11/08)。
一方、発がん性リスクがあるのに製品に表示しなかったとして懲罰的損害賠償が大きな争点になっている発がん性裁判の方は混とんとしたままだ。2022年6月に連邦最高裁が被告(バイエル社)の上告を受理しなかったため、原告勝訴が確定したことは、当コラム(2022年7月27日)で紹介した。
集団訴訟がどのように決着するのか不明だが、個別の裁判も1年に数件のペースで行われている。2021年から2023年9月まで、一審の陪審員裁判で、原告の訴えが9回続けて棄却され、バイエル社が勝訴した。しかし、10~12月の陪審員では5連敗だ(バイエル社の裁判特集サイト)。
メディアはバイエルが敗訴し、特に賠償金額が高額の時だけ報道し、バイエル勝訴の場合はほとんどニュースにしないので、世間には全体像が伝わらないようだ。陪審員判決の傾向や懲罰的賠償金額の根拠もさまざまで、これからの個別裁判の方向性は見通せない。
グリホサートは多くの雑草に効果があり、環境への影響も他の製品に比べて比較的小さい除草剤だ。毎年同じ畑に連用すると抵抗性雑草が生じるが、管理して上手に使えば、現時点では優れた薬剤の部類に入る。残念ながら、グリホサートに代わる効果的な製品は今のところ開発されていない。
ヨーロッパのドタバタ劇や米国の裁判でわかるように、グリホサートは科学的に安全性を考えるのではなく、活動家や政治家を活気付かせ、それにメディアも連動する社会現象になっている。ヨーロッパはこの先どうなるか読めないが、「10年延長反対」という市民団体の請願運動(市民イニシアティブ)が予想される。米国でも当分、裁判がらみの話題としてメディアを賑わすだろう。

1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー
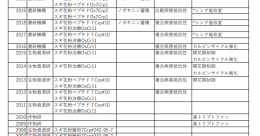 政府の花粉症対策まとまる 主役から外れた花粉症緩和米はどうなるのか?
政府の花粉症対策まとまる 主役から外れた花粉症緩和米はどうなるのか?  国産大豆に極多収品種登場 自給率向上は期待できるのか?
国産大豆に極多収品種登場 自給率向上は期待できるのか? 一時、話題になったけど最近はマスコミに登場しないこと、ほとんどニュースにならないけど私たちの食生活、食料問題と密に関わる国内外のできごとをやや斜め目線で紹介
