新・斎藤くんの残留農薬分析
残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。
残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。
 斎藤 勲
斎藤 勲台湾で今年8月より、日本からの輸入メロンの農薬検査違反が報道されている。今年2月にはいったん違反事例報告が途絶えたが、また輸出の季節になったので検査したら違反ということらしい。違反率が上がっているので、10月31日までは検査率を20~50%(特定業者は100%)で検査するとのこと。
なぜ、違反が頻発するのだろうか。
台湾の検査は果皮を含む全果での検査で、台湾での農薬の適用がないものが多く0.01ppmの基準が適用されて違反となる事例が多い。
2023年11月にもこのコラム(北海道メロンが台湾で違反、気になることがある – FOOCOM.NET)で台湾での北海道メロンの違反報道について解説したが、今年も北海道産の「らいでん」メロン等が違反となっている。
前回問題となっていた農薬フェニトロチオン(スミチオン)は、令和7年2月10日の規格基準の一部改正令和7年2月10日消食基第70号・令和7年2月21日消食基第137号(一部訂正)で、従来皮をむいたり除いて検査していたミカン、スイカ、メロン、モモなどが皮ごと(全果)の検査部位となり、それに伴い基準値もメロン15倍、スイカ10倍、みかん140倍、もも20倍に引き上げられた。こう書くとこの部分だけ取り上げられそうだが、これでフェニトロチオンの基準値改正はほぼ終了した感じだろうか。
しかし、台湾に輸出するとなると基準値が全果で0.01ppmであり、台湾に輸出するなら使うことはできないし、ドリフトさえ要注意である。今回のメロンのフェニトロチオン0.33ppm違反も基準値の33倍も残留していると現地では報道されている。
今年に入ってから違反となっているメロンは、産地としては北海道、静岡、熊本、愛知、島根である。農薬は、テトラニリプロール3件、ニテンピラム3件、イプロジオン2件、メパムピリム、フェニトロチオン各1件。近年日本のメロンの検査部位が果皮を含む全果の基準に変わりつつあるが、まだメロンの農薬基準全体の35%くらいである(イプロジオン2024年改正8ppm、メパムピリム2023年改正2ppm、フェニトロチオン2025年改正0.02ppmは果皮を含む全果での基準)。残念ながらニテンピラムは2017年の基準値改正で従来の暫定基準値5ppmから作物残留試験などの結果を受け0.7ppmとなったが、日本での検査部位は果皮を含まない検査である。
違反となったメロンの重量は各ロット3kg~528kg、合計1.37トンである。高級メロン1000個以上である。フェニトロチオン基準0.01ppm以外は不検出基準で0.01ppm未満が適用され違反廃棄、もったいない話である。
毎年、こんな無駄な状況を繰り返していても意味がないことは誰でもわかっているだろう。しかし、台湾の残留基準値がすぐ変わるわけでもない以上、台湾に日本の高価なマスクメロンを売りたいなら、やることはただ一つ。出荷する業者が、台湾の残留基準値を熟知し、生産地レベルでの農薬使用履歴の把握、それに基づく0.01ppmが十分検出できる感度での残留農薬検査が必須である。
生産地レベルといったのは、メロンの場合ハウス栽培が多いのでドリフトは大丈夫かもしれないが、果皮を含む検査でなおかつ0.01ppmレベルなので用心するに越したことはない。一番いいのは不検出0.01ppm基準の農薬は使わないのが一番いいが、台湾だけに輸出してるわけではないのでそれも困るだろう。
正直なところ、メロンの輸出数量、輸出金額の9割近くが実は香港に輸出されている。しかし、香港で日本のメロンの残留農薬違反が頻発しているとは聞いたことがない。香港も台湾同様残留基準は設定しているが、台湾同様多くはない。
香港では、放射性物質検査(まだ行われている)、メチル水銀、カドミウム、鉛など金属汚染物質、衛生状態管理など、放射性物質を除けば実際にリスクのあるものの検査が主流だ。残留農薬検査違反などは、報告数が少ない。
香港では1987年、中国本土から100ppmを超えるメタミドホスが残留した白菜で食中毒が発生した事件があり、残留農薬問題に関心がないわけではない。2023年4月、台湾で相次ぐ日本産イチゴ違反 香港では? – FOOCOM.NET のコラムで香港の検査体制について述べたが、農薬の残留基準値のないものが検出された場合は安全性などを評価してケースバイケースで対応するようである。この考え方なら、台湾の事例はすべてスルーだろう。
同じメロンがこれほど国により対応が異なるならば、検査費用などを上乗せして少し高価なメロンを台湾に輸出するしかないだろう。
私の知り合いの安藤 孝さんという方が、宮崎市の閑静な住宅街の一軒家を改造してfiroという検査施設firo|株式会社食品検査・研究機構 – Food Inspect & Research Organizationを立ち上げ、輸出にかかわる残留農薬検査をはじめ、様々な受託検査を迅速に行っている。彼も台湾メロンについて情報発信を行っており、諸外国の検疫検査の状況などに詳しい。
余談になるが、台湾衛生福利部食品薬物管理署の違反情報を見ていると、今年のメロンは鮮蜜瓜(FRESH MELON)として記載されている。しかし、昨年は鮮哈密瓜(FRESH MELON)と半々であった。載っている写真を見ても、両方とも日本でいうマスクメロンであった。
調べてみると、「蜜瓜(ミグワ)」はそのまま訳すとハネジューメロン(滑らかで淡い色の皮と緑色の果肉)が出てくるが、日本のネットメロンもこの名前で呼ばれているようで紛らわしい。「哈密瓜(ハミグワ)」は本来新疆ウイグル自治区産のハミウリでラグビーボールのような形とネット状の皮が特徴とのことだが、市場では日本のメロンは蜜瓜、哈密瓜の両方使われるようだ。
台湾で栽培されるメロンは「香瓜」「美濃瓜」などと呼ばれ、日本のメロンよりも小さく甘さはひかえめ、瓜にちかい味だという。輸入の日本メロンは甘く「蜜瓜」と区別されて呼ばれる高級品である。
それが残留農薬違反でイメージがダウンし、しかも廃棄されるのはどうしたものでしょう。

地方衛生研究所や生協などで40年近く残留農薬等食品分析に従事。広く食品の残留物質などに関心をもって生活している。
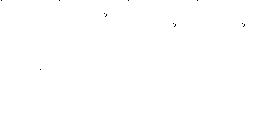 EWG 残留農薬のダーティ・ダズンを毎年公表する意味があるのか?
EWG 残留農薬のダーティ・ダズンを毎年公表する意味があるのか? 残留農薬分析はこの30年間で急速な進歩をとげたが、まだまだその成果を活かしきれていない。このコラムでは残留農薬分析を中心にその意味するものを伝えたい。
