野良猫通信
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
 畝山 智香子
畝山 智香子米国の消費者組織の雑誌であるConsumer Reportsが本年10月、近年流行しているプロテインパウダーとプロテインシェイクに高濃度の鉛が含まれると発表しました。
Protein Powders and Shakes Contain High Levels of Lead – Consumer Reports
By Paris Martineau Published October 14, 2025
プロテインパウダーに有害重金属が含まれるという発表はこれが初めてというわけではなく、今年2月にも以下の記事で紹介しています。
プロテインパウダーに有害金属? – FOOCOM.NET
2025年2月5日
2月の発表は認証ビジネス事業者の宣伝色が強いものですが、今回は消費者団体の製品検査という形をとっています。ただしどちらもカリフォルニア州法のProposition 65の安全閾値を指標としているという共通点があります。
どうしてFDAやEPAなどの連邦機関ではなくカリフォルニア州なのか?それはカリフォルニアのProposition 65が最も低い「安全性の目安」となる値を使っているからです。
Proposition 65は正式名称を「1986年安全飲料水および有害物質施行法」といい、1986年に市民の要請によってつくられた法律です。化学物質によるがん、先天性障害、生殖への悪影響を予防するために、いろいろな消費者製品に警告表示を要求します。
一見、科学的に正しそうなのですが、問題はその評価方法が多くの場合過剰に予防的であるため、あらゆるものに警告表示がついてしまうことです。例えば日本のお煎餅は原料のコメに由来するヒ素がカリフォルニア基準では警告対象になることがよくあります。販売禁止というわけではないので警告シールの貼ってある製品を普通に食べる、わけです。結果的に警告があっても気にしないようになってしまって、本当にリスクが高いものの警告でも無視されてしまう可能性が高くなっています。
鉛についてはもともと有害であることは明確ですが、問題はどのくらいの濃度で警告表示が必要か、です。
カリフォルニア州の鉛についてのページによると
Lead – OEHHA
がんについては 有意なリスクがない量No Significant Risk Level (NSRL) -経口で:15 µg/day
生殖毒性については 最大許容量Maximum Allowable Dose Level (MADL) -0.5 µg/day
この低い方の0.5 µg/dayという値がConsumer Reportsなどが使っている値です。
国際的なリスク評価機関であるJECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)は、鉛の健康影響評価について1999年にPTWI (暫定耐容週間摂取量)を25 µg/kg bwと評価しましたが、2011年に「安全な量を設定できない」にしています。
WHO | JECFAによる「鉛」の評価
FDAは2020年に暫定参照用量interim reference levels (IRLs)として子供には3 µg/day 、生殖年齢の女性には 12.5 µg/dayを設定し、2022年にそれぞれ2.2µg/day および8.8 μg/dayに更新しています。子供と生殖年齢の女性が対象なのは鉛の最も感受性の高い有害影響が子供の知能の発達への影響だと考えられているからで、メチル水銀の場合と同様です。
Guidance for Industry: Action Levels for Lead in Processed Food Intended for Babies and Young Children | FDA January 2025(なおこの時のFDAはまだまともだった)
日本では食品安全委員会が2021年に鉛に係る食品健康影響評価を行ってQ &Aを公開しています。
「鉛」の評価書に関する情報 | 食品安全委員会 – 食の安全、を科学する
評価の結果として有害影響を及ぼさない濃度(耐容摂取量)の設定は困難である、とされています。ただし現在の日本における平均的な血中鉛濃度は1μg/dL程度で、食事からの摂取量は2019年の研究で8.88 µg/日と、FDAの生殖年齢の女性向けIRLと同程度です。
鉛については有害影響の可能性がある量と実際に人々が摂取している量がかなり近く、低減のためのリスク管理の優先順位が高い、ということには科学的コンセンサスがあります。しかしながら鉛は地球上に天然に存在する元素で(それこそ永遠に無くなることはない)、ほとんどの食品にごく微量存在することは避けられないため、食料安全保障などとの兼ね合いを考えながら実行可能な対策を地道に続けるしかないのです。
幸い日本人の現状の摂取量で鉛による明確な有害影響がでているという状況ではないので、落ち着いて慎重に対処すべきです。
こうした値に比べるとカリフォルニアのProposition 65の数値は小さいです。
カリフォルニアが他の評価機関より厳しい値を出す理由は、州の法律にあります。
Proposition 65 Law and Regulations – OEHHA
1989年に定めた安全な量を計算するための方法に
Final Statement of Reasons Sections 12701 and 12801 (NSRLs and NOELs)
1000倍のばく露量を想定しても全く影響が出ない量、つまり無影響量(NOELs)に1000倍の安全性係数を使うと決めてあるのです。
一般的なリスク評価機関が安全性評価で使う安全係数は、動物実験の場合には100でヒト試験の場合には10です。もちろん安全係数1000を使う場合もあります。しかしProposition 65ではデフォルトで安全係数が大きく、そのとにかく安全側に寄せるという考え方は評価プロセス全体にかかる基本方針なので、多くの場合「世界で最も厳しい値」を導出するのです。
別の言い方をするとProposition 65の数値は現実的なリスクを反映していない、わけです。
鉛は最初からProposition 65のリストにあり、0.5 µg/dayは法律ができた当初から普通の食品などで超過する場合があるとして異議申し立てなどされてきました。しかし「鉛」はばく露量を減らしたほうがいい有害物質であるという科学的コンセンサスがあるため、裁判でひっくり返すことはできませんでした。
Consumer Reportsの「鉛」警告にはもう一つ背景があります。
2025年10月19日から25日にかけて、第 13 回 国際鉛中毒予防週間 (ILPPW)でした。そして2025年のテーマが「安全な鉛レベルは存在しません : 今すぐ行動し鉛ばく露を終わらせましょう」です。
No safe level: act now to end lead exposure 17 October 2025
WHOが主な対象としているのは鉛中毒の症状が実際に出るような、鉛塗料や有鉛ガソリンなどに由来する、より高濃度の鉛ばく露です。しかしこのスローガンは、どんなわずかな量でも危険だというメッセージになっています。
つまりConsumer Reportsのような活動への援護になります。危機感を高めることで対策を後押ししたいという気持ちがこのスローガンになったのは理解できますが、これでは鉛ばく露量の比較的低いところでさらに低くするためにリソースを費やすことを促し、よりリスクの高いところに配分すべきリソースが減ることにつながりかねません。
世界は多様で、WHOは全体に向けてメッセージを出すために相手によってはあまり適切でない場合がよくあります。具体的な相手や数値を明示しないスローガンは科学というより政治に属するものだと思います。それが「WHOが言っている」を大義名分にしたくない理由のひとつです。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
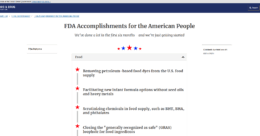 この半年間で米国FDAが「達成」したものとは?
この半年間で米国FDAが「達成」したものとは?  標準測定法がないのに「多い」と報道されるマイクロおよびナノプラスチック
標準測定法がないのに「多い」と報道されるマイクロおよびナノプラスチック 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
