野良猫通信
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
 畝山 智香子
畝山 智香子2025年7月17日に日本弁護士連合会からサプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書が提出されました。
日本弁護士連合会:サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書
趣旨は以下のようなものです(HPから)。
また関東弁護士会連合会は7月22日付で機能性表示食品に関する意見書を発表しています。
機能性表示食品に関する意見書: 宣言・決議・声明 | 関東弁護士会連合会
趣旨は以下です。
これらに関連した最近の海外情報を紹介しておきます。
2025年4月、FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations、国際連合食糧農業機関)から「個別化栄養における食品安全」という報告書が発表されました。
Food safety in personalized nutrition
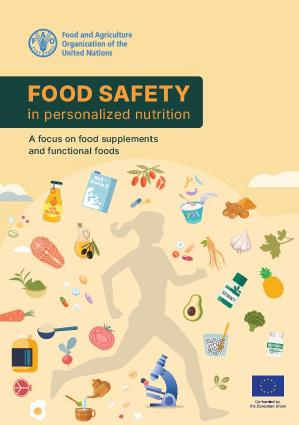
プレスリリースは以下です。
安全な革新を支援する:FAOは食品サプリメントと機能性食品あるいは健康食品の安全性の検討を強調する
Supporting safe innovation: FAO highlights food safety considerations for food supplements and functional or health foods
29/04/2025
内容はいわゆる健康食品の規制や消費者の認識などについての現状と安全上の課題をまとめたもので、世界中の事例を多数紹介しています。
これらの安全性の問題としては以下の項目をあげて説明しています。
このうち汚染物質の項目で日本での紅麹を含むサプリメントによる健康被害事例を紹介しています。製品の摂取と関連する可能性のある死亡が100人を超え、400人以上が入院したと記述されていて、他の多数の紹介されている事例の中でも大規模で深刻なものであることが改めて認識されます。
この報告書ではかなりのページを割いて医薬品との相互作を紹介しているのが印象的です。
ドイツBfRが定期的に刊行している科学読み物BfR2GOの2025年第1号が食品サプリメント特集でした。
BfR2GO, Issue 1/2025, Main topic: Food supplements – BfR
18/07/2025
表紙の文章は「食品サプリメント:誇大広告と誤解」、特集の見出しは「誇大広告と誤解の間Between hype and misconception」です。そして消費者調査の結果から、食品サプリメントによくある5つの誤解として以下が明らかになったとしています。
章のまとめは「食品サプリメントを使用している人の数は、それらへの誤解と同じくらい多い」とあります。つまり食品サプリメントの需要の多くは誤解によるもので、食品サプリメントが繁栄する場所は「誇大広告と誤解の間」であるので、正確な理解が普及していれば食品サプリメントの使用はそれほど多くはならないはずだというわけです。
この「誇大広告と誤解の間」という表現が健康食品の本質をついていておもしろかったのでタイトルにいれてみました。
EUの食品サプリメント規制は比較的厳しく、ヘルスクレームも認可されたものしか使うことはできないのですがそれでも誇大宣伝による誤解が広がっているのが実情です。
これらの文書からは、国際的にも、国が違っていても、いわゆる健康食品が、医薬品と食品の境界付近で、誇大広告と安全性の点で問題になっていることがわかります。サプリメントの性質からは当然のことです。
そして日本の保健機能食品制度においては、食品は病気の人が使用するものではないという主張の下で医薬品との相互作用についての考慮が不足していることも明らかです。日本でも医薬品と同時に健康食品を使っている人がそれなりにいることは報告されています。サプリメントそのものの安全性はもちろん、それを使う人がどういう人なのか、その人たちにとって安全なものにするためにはどうしたらいいのか、まで考えることがいわゆる健康食品による健康被害を防ぐためには必要です。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
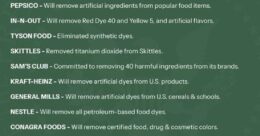 MAHA報告書その後(2)
MAHA報告書その後(2)  スチレンのリスク評価―IARCのハザード評価を重視すべきではないもう一つの例
スチレンのリスク評価―IARCのハザード評価を重視すべきではないもう一つの例 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
