野良猫通信
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
 畝山 智香子
畝山 智香子さてLancetの超加工食品シリーズを受けて、WHOの超加工食品ガイドラインが似たような内容になる可能性があることは既に指摘しました。
それ以外の最近の周辺情報についてまとめてみます。
アメリカではUSDAとFDAが超加工食品(UPF)についての定義をするという発表が2025年7月25日にあり、情報募集期間を一度延長して2025年10月23日までとしていました。
Federal Register :: Ultra-Processed Foods; Request for Information; Extension of Comment Period
これに対して全国チキン評議会National Chicken Council (NCC)が提出した意見を公開しています。
NCC-Comments-on-UPF-RFI_Oct2025.pdf
10月に政府機関の閉鎖が始まり11月まで40日間続いたためこれが現在どうなっているかは不明です。ただ業界団体は現政府の中で何がどう決められるかわからないので、NCCのように消費者に向けて意見を出せばいい、とは思います。
つなぎ予算では超加工食品研究予算がカットされたとの報道Shutdown Deal Kills Food Safety Rulesもありました。
一方で、延び延びになっていたアメリカ人のための食事ガイドライン2025-2030が12月中に発表されるとHHS長官が繰り返し述べているようで、その中でUPFがどう言及されるのかは注目です。ただアメリカで現在最も関心が高いのは動物性脂肪を巡る話題のようで、これまで摂取を抑制するように言われ続けてきた動物由来の飽和脂肪酸摂取が逆に推奨される可能性が高いと予測されています。
UPFに関する議論もこれに関連があり、NOVA分類では動物の肉はステーキなどで食べるならUPFではないので積極的に推奨され、一方植物由来の成分で作った肉代用品はUPFなので食べない方がいいとされます。一般的に米国では栄養学的理由と環境負荷の点から、肉を食べるより植物ベースの代用品を薦めてきました。それがアメリカを再び健康にする(MAHA)運動とNOVA推進の二つの方向から植物より肉を推奨、になってしまう可能性があります。このMAHAとNOVAの一致はアメリカ人の健康にとって悪い方向に働くとしか思えませんが、NOVAの本質が健康のためというより社会運動である側面を象徴する事象とも言えます。
完全菜食主義(ビーガン)を推進している団体は、ビーガン用の植物ベースのミルクや代用肉などがUPFに分類されると認識し、ビーガン用食品はUPFではないと独自に主張してみたり、食事中UPFの割合が高くても菜食の人の肥満は少なく健康状態が悪いことはないと反論したりしているのですが、あまり大きな声にはなっていないように見えます。バブルが突然弾けたばかりということもあり、代用肉業界にとっては今は厳しい時代だろうと思われます。
Lancetのシリーズは超加工食品規制の声が非常に大きくなったと感じるイベントかもしれませんが、逆に今推進しないとそのうち関心が薄れるだろうという危機感の表れとも感じます。というのは米国を中心に、抗肥満薬の使用者が急増していてその効果が実感されつつあるのです。栄養学者による食事助言は肥満の増加に対する歯止めにはならなかったけれど、医薬品が状況を一変させた、と多くの人が実感するまであと少し、というわけです。NOVA分類の推進者が、効果があるかどうかわからないたくさんの規制を提案する一方で医薬品が明確な成果をあげている。だったら医薬品にリソースを配分した方が効率が良いのではないか、と考えられるのは当然です。
いずれにせよ肥満大国の行方がどうなるのかは今後しばらく注視する必要があるでしょう。ちなみに心血管系疾患のリスク要因である脂質異常症についても、食事助言ではなかなか改善されなかったものが抗高脂血症薬によって劇的に改善されたという前例があります。
日本は最初から蚊帳の外なのですが、Lancetシリーズの主張を読んで、NOVA分類は日本の食の状況には全く役に立たないと改めて思いました。
素材から料理して食べる以外のほとんどのものがUPFに分類されるのですが、お惣菜や中食、あるいは冷凍食品は日本の食卓を豊かにしてくれる重要な要素です。そしてお惣菜の製造業者は「グローバル大企業」はむしろ少なく、たくさんの中小食品企業です。数多くの合わせ調味料が販売されているおかげで家庭で野菜の料理が簡単にできる場合もあるでしょう。
レストランで食事をすればUPFは含まれないなどという想定も違っていて、チェーンレストランではセントラルキッチンで調理したものを温めるだけ、の場合も少なくないはずです。そして加工食品を使わずに料理をするようにという政策が実施された場合、「料理をする人」は一体誰なのでしょう?
今後さらに高齢の一人暮らしの人が増えるだろう日本社会においては、食べやすく栄養のある出来合いの料理が手軽に買えることは重要な社会インフラです。硬い食品を柔らかくしたり飲み込みやすくとろみをつけたりするのに食品添加物は有用ですし、見た目が良いことも食事の楽しみの一要素です。
さらに重要なことは災害の多い日本では、保存のきくすぐ食べられる食品は必要なものです。ローリングストックは合理的で、もっと世界にも広めるべきです。NOVA分類の発祥地でNOVA分類が政策に取り入れられているブラジルでは、災害に遭って水も燃料も入手できない状況であっても調理しないと食べられない豆や穀物などが食料援助として届けられるそうですが(https://www.linkedin.com/pulse/from-fairy-tale-global-nightmare-what-nova-refuses-see-marcia-terra-z8qsf/?trackingId=XPE96ZG%2FQICnZIOhsfUGGg%3D%3D)、それを望ましいと思う日本人はいないのではないでしょうか。イデオロギー先行で人々が困っていることを気にしない公衆衛生の大御所、とはいったい何なのだろうと思います。
そしてLancetシリーズに賛同する世界の公衆衛生研究者たちの意見を見ていて最も日本にあてはまらないと思ったのは、「食品選択を消費者に任せていてはだめだから政治が強制すべき」という主張です。日本の消費者はいままでもこれからも、自分の食べるものを自由に選択したうえでなお健康でいられる、と私は思います。だから情報提供が役に立つと信じています。
新型コロナウイルス感染症対策の時にも感じたのですが、国民への信頼がないと法による強制、という発想になるのでしょう。日本はそういうのは見習わなくていいのではないでしょうか。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
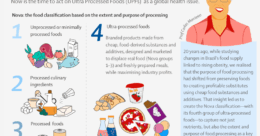 Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その2) 3つのレビューの内容
Lancet「超加工食品シリーズ」の問題点(その2) 3つのレビューの内容 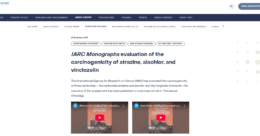 IARCモノグラフによる科学の冒涜―モノグラフ140のアトラジンハザード評価について
IARCモノグラフによる科学の冒涜―モノグラフ140のアトラジンハザード評価について 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
