野良猫通信
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
 畝山 智香子
畝山 智香子プラセボ効果という言葉を聞いたことがあると思います。何も有効成分が入っていない偽薬であっても、患者が薬を飲んだと信じると症状が改善するなどの実際の効果がみられる現象のことです。医薬品の有効性評価において考慮する必要があるため、多くの研究がおこなわれています。
逆にこれは悪いことがおこるに違いないと信じている場合に有害影響がおこるのはノセボ効果といいます。プラセボとノセボは人体の不思議さを再認識させる効果ですが、当然のことながらなんでもありというわけではなく、骨折のような物理的な現象にはあまり影響しません。
食品への反応はどちらかというと効果がでやすいもので、いくつかの研究がありますが、最近発表された研究を紹介します。
過敏性腸症候群の成人の症状と行動に与えるグルテンと小麦の影響:単一センター、無作為化、二重盲検、偽対照クロスオーバー試験
Effect of gluten and wheat on symptoms and behaviours in adults with irritable bowel syndrome: a single-centre, randomised, double-blind, sham-controlled crossover trial – The Lancet Gastroenterology & Hepatology
カナダMcMaster大学の研究者らによる研究です。
研究の参加者は、18才以上で過敏性腸症候群(IBS)で、グルテンフリー食にすると症状が改善すると自己申告した人たちです。介入は小麦、グルテン、小麦とグルテンを含まない(対照)の3種類のうちどれかを7日間、14日間の洗浄期間を経て7日間別の介入、さらに14日間の洗浄期間のあと7日間介入というやりかたです。
グループは小麦–グルテン–対照 (n=5)、 小麦–対照–グルテン (n=5)、グルテン–小麦–対照 (n=5)、 グルテン–対照–小麦 (n=5)、対照–小麦–グルテン (n=5)、 対照–グルテン–小麦(n=4)の順番で投与された6つになります。参加者は全ての介入時に小麦を含む食品を食べていると考えているはずです。グルテンが症状の悪化に関係するのであればグルテンと小麦の投与時に症状が悪化し、対照の時には悪化しないはずです。
しかし結果は小麦でもグルテンでもそれらを含まない対照でも、介入があれば全て同じように症状が悪化しました。研究者らはこの結果を、患者が症状の悪化を予期することが症状を生み出す主要な要因であると解釈しています。そしてグルテンや小麦を制限することが役に立つ患者は少ないのだろうと考えます。
この研究の筆頭著者のCaroline Larissa Seiler博士は、この研究について一般向けに解説も書いています。
Analysis: The ‘nocebo effect’ in IBS: Why gluten might not be the real problem – Brighter World
By Caroline Seiler November 1, 2024
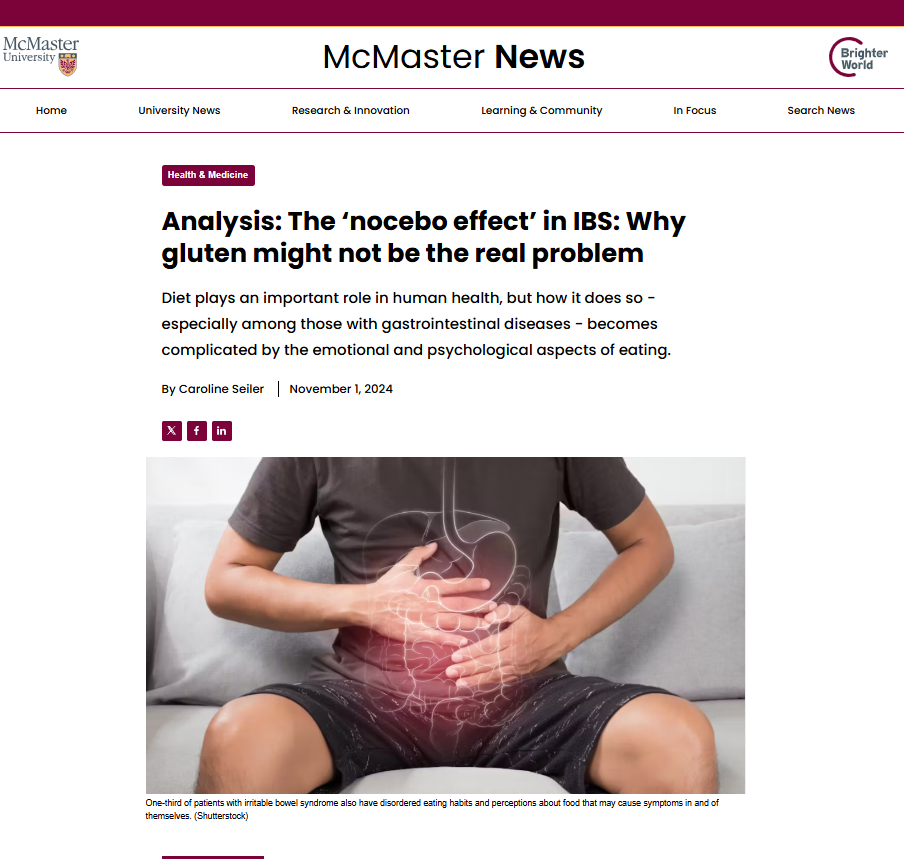
食事が健康にとって重要であることは間違いないものの、消化管症状については心理的側面も大きく複雑であることがわかっています。特に近年欧米を中心に小麦に含まれるグルテンがお腹に悪いという説が流行していて、セリアック病ではないグルテン過敏症が増えています。消化管に目に見える悪いところがないもののグルテンや小麦を食べるとお腹を壊すと訴える患者さんに対して、医師や栄養士は小麦やグルテンを避けるように助言することになるのですがそれは患者の生活を相当不便にします。しかしMcMaster大学の栄養研究者の研究によると小麦やグルテンで症状が悪化すると訴える患者さんの症状は、グルテンがなくてもグルテンが入っていると思い込むことで現れる症状―つまりノセボと差がないのです。
こうした結果は全く新しいものではなく、既に似たような結果が世界中から報告されています。中でも英国とオランダの共同研究による無作為化二重盲検プラセボ対照研究は明確にノセボ効果を証明しています。
The effect of expectancy versus actual gluten intake on gastrointestinal and extra-intestinal symptoms in non-coeliac gluten sensitivity: a randomised, double-blind, placebo-controlled, international, multicentre study – The Lancet Gastroenterology & Hepatology
この研究ではグルテン過敏症だと報告した患者さんにグルテンを含むパンとグルテンを含まないパンを与えます。それぞれさらにふたつにわけてグルテンを含むという情報とグルテンを含まないという情報を与えます。その結果グルテンを含むことを伝えられてグルテンを含むパンを与えられた群の症状が他の3群に比べて悪かった。
つまり「グルテンを含むという情報」(患者はそれによって症状が出ることを予想する)が症状の悪化要因になっているというわけです。
これは食に関する「〇〇は身体に悪い」という類の間違った情報には、実害があることを意味します。間違っていてもとりあえず警告することには害はないという主張は間違いです。念のため、悪いという情報は根拠がなくても積極的に集めて信じておけば安心、と考えている人がいるとしたら、それは自ら呪いにかかろうとしているようなものです。
ノセボ効果は確実に「ある」のです。問題はSeiler博士のこの研究のフォローアップについての知見で、患者さんにあなたの身体症状はグルテン特異的でないという個別の結果を伝えた後でも、少なくとも6か月は自分はグルテンに反応するのだという信念を持ち続けていたということです。これは一度思い込んだ信念はそう簡単には変わらないことを示します。ノセボ効果は呪いのようなものですが、その呪いは簡単には消えないのです。
プラセボ効果にも、プラセボであることがわかっていても効果が出るという報告があります。自分の心だから自分がコントロールできる、わけではないのです。
甘味料のアスパルテームについても、自称過敏症の人は実際にアスパルテームに反応しているのではないことが英国FSAによって確認されています。
Determination of the symptoms of aspartame in subjects who have previously reported symptoms compared to controls: a pilot double blind placebo crossover study | Food Standards Agency
19 March 2015
それでも食べると気分が悪くなる、身体症状が出る、という主張はネットに溢れています。
そうしたネガティブ情報は無害ではない。おそらく書いた人自身にとってもノセボ効果を強化する悪影響があるでしょう。
ノセボ効果は、正確な情報こそが重要であることを再確認するものです。

東北大学薬学部卒、薬学博士。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長を退任後、野良猫食情報研究所を運営。
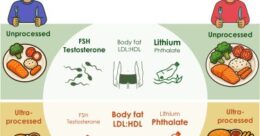 大学や研究者が科学への信頼を損なう例―超加工食品研究
大学や研究者が科学への信頼を損なう例―超加工食品研究 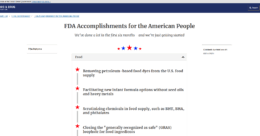 この半年間で米国FDAが「達成」したものとは?
この半年間で米国FDAが「達成」したものとは? 国内外の食品安全関連ニュースの科学について情報発信する「野良猫 食情報研究所」。日々のニュースの中からピックアップして、解説などを加えてお届けします。
